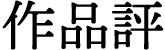1983年2月に公開された『ションベン・ライダー』に、当時高校生だった河合美智子が演じたブルースというキャラクターが存在する。ブルース・リー譲りの格闘技の使い手で、必殺技は飛び蹴り。永瀬正敏演じるジョジョ、坂上忍演じる辞書の3人組で行動し、親のトラブルに巻き込まれてヤクザに拉致された学校一のいじめっ子、デブナガを、虐められていた落とし前をつけるために取り返しの旅に出る。ブルースはベリーショートで、シャツに短パンというマニッシュな装いだ。監督の相米慎二は「男か女かわからないようなブルース」という言葉を残している(「相米慎二 最低な日々」より)。LGBTQという言葉が世に定着する前のことで、その概念も理解もまだまだ及んでいない時代に、ティーンエイジャーの同世代の観客に向けてはっきりとした輪郭で描かれた性的マイノリティの先駆的な人物と言えるだろう。どうしてこのような人物を生み出したか経緯はよくわからないが、劇中、ボクと言っていたブルースが、初潮を迎えたことに気づき、熱海の海中へと入っていく場面がある。性自認は男性だが、女性としての肉体を意識せざるを得ない生理を迎えて混乱したのか。それともまだ性自認が男性なのか女性なのか意識していない段階での戸惑いなのか。残念ながら、この映画はデブナガの救出劇という本筋に戻り、ブルースのセクシャリティについての顛末には特に触れられないまま終わってしまう。相米監督が投げっぱなしにしたブルースのその後の物語は、後世の映画人たちに任された形になったのである。
日本映画史の流れの中にぽんと放り投げ込まれた球を、30年以上の月日を経てしっかりと受け止め、世に作品を送り出している映画人が増えてきているが、その筆頭が飯塚花笑監督である。
2011年、第33回ぴあフィルムフェスティバル(PFF)で審査員特別賞を受賞した『僕らの未来』は飯塚が監督・脚本・撮影・編集を手掛けた初監督作。主人公の優(日向陸)は女性の肉体に生まれついたが、高校生となった今、自分は男性であると明確な性自認がある。学校で定められたスカートを無条件にはいて通学することは自らのセクシュアルアイデンティティを否定することであり、スカートの下にジャージをはいて学校の夏期講習に通うが、教師にも、級友にも理解されず、ときにあからさまな侮蔑の言葉を投げつけられる。他の生徒と同じように、自分らしく学校で過ごしたいという人としての権利が無遠慮に踏みにじられる様子が、生々しさと共に描かれる。そこには当事者として体験した痛みが込められ、同じような周囲の無理解にさらされる全国の優たちへの「君だけじゃないよ」という呼びかけが込められた作品だった。
文部科学省は2015年4月に「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」という通知を各教育委員会等に発出した。それを踏まえ、2016年 4 月には「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施について(教職員向け)」というリーフレットも出し、教育の場で性の多様性を認め、セクシャルマイノリティへの支援の在り方にも言及している。残念ながら飯塚監督はその対応に間に合わなかった世代であり、だからこそ、『僕らの未来』で紡がれた優の抱えるジレンマは貴重な歴史の証人ともいえる。
まだ同性婚が認められていない2022年の日本に発表される『フタリノセカイ』も、いつか同性婚が当たり前となった時代に至るまでの、ミッシングリンクの役割を果たす作品と言える。
飯塚監督のアバターともいえる真也を演じるのは坂東龍汰。昨今、LGBTQの人物を、シスジェンダーの俳優が演じることについての議論は絶えず、『リリーのすべて』にて、世界で初めて性別適合手術を受けた実在人物をモデルとした主人公を演じたエディ・レッドメインは去る11月、イギリスの新聞『The Sunday Times』で「今だったら、あの役を引き受けない」と話したと話題を呼んだが、そこには、制作年の2015年から6年余り経つ中で、トランスジェンダーの俳優の活躍を望む土壌と理解がかなり拡大したことを示してもいる。飯塚監督は今回のキャストを考察する際、2015年製作の『トランスアメリカ』が頭にあったという。肉体的に女性となる最後の手術を控えたトランスセクシュアルのブリーを、シスジェンダーのフェリシティ・ハフマンが演じているが、当事者の内面を表現する圧倒的な説得力に感銘を受け、演じる人間の性別が重要なのではなく、個々の俳優の表現力が最優先されるべきだと考えたという。真也は性同一性障害の診断を受け、すでに医療機関で男性ホルモンの投与を受けている段階で、外見的には男性にしか見えない。坂東を選んだのは、彼の表現力に期待値が高かったことと、やや高い声がトランス男性の特徴と重なり合うということも大きかったという。
今作のもう一人の主人公である結(ユイ)は、真也との出会いで、それまでの人生で想像してこなかったセクシャルマイノリティとの交際を経て、どう未来設計図を作るのかというフェーズに入る。二人の間にはセックスの問題があり、家族として社会にどう認められるかの法整備の問題とぶち当たり、なにより子供を持ちたいという願いに対してどういう選択をするのか、今現在の日本に暮らす中で必ず浮き上がってくる問題をひとつずつ抽出し、その都度、噴出する感情の衝突を描いている。飯塚監督は真也と結の出会いの場所をわざわざ保育園という場所に設定している。子供と一緒にいるという日常を二人が望むのは難しいことなのか。当初、素敵な男性に一目ぼれの恋をして、まるで少女コミックの主人公のようにふわふわとした雰囲気をまとっていた結が、真也がセックスの段階で踏み込んでこない不信感や、彼が肉体には女性であることを知った戸惑いなどで、激しい感情を露わにしていく。その変貌こそが、結役の片山友希に託されたもの。二人の思いが真剣で、真っすぐだからこそ、感情がぶつかった摩擦は激しく、大きい。
真也と結の関係性の重要な潤滑油となる存在として、飯塚監督の過去作の『青し時雨』『海へゆく話』、そして来年公開作『世界は僕らに気づかない』と出演が続く松永拓野が扮しているのも、飯塚監督の描く世界観がどう変わっていくか、定点観測のひとつの起点として見逃せない。
フィリピン出身のトランスジェンダーのフィルムメイカーであるイザベル・サンドバルは、e-flux Journalに寄稿した「Seeing as the Other」(※1)という文章の中で、「トランスの映画製作者としての私の最優先事項は、シスジェンダーの観客の持つ解釈の修正である」と自身の考えを書いている。飯塚監督も同じチャレンジをしているが、同時に自身と同じ境遇で揺らぐ当事者たちへのエールも両立させようともがいている。正直、監督の思いが強すぎて解説的に見える場面があったり、登場人物の台詞での説明が多いなどまだまだ未成熟な演出部分も見受けられるが、彼のような作家は、一作ごとの評価ではなく、作り続け、年齢を重ねていくことで、多くの観客に力を与える世界観を提示する作家だと考える。彼の果敢な挑戦はまだ始まったばかり。彼が日本映画史において今回投げかけた白い球は、次はだれが、どこで、どう受け止めて、また放たれるのか。私たち観客は、その球の行方から決して目を離してはいけない。
※1 https://www.e-flux.com/journal/117/385174/seeing-as-the-other/